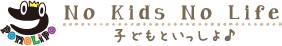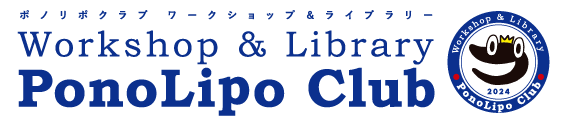少子高齢化の進行とコロナ禍を経て、社会が大きく変化してきたことを子育て世代の家族と接する中で、日々実感しています。ニュースでも大きく取り上げられている不登校児童生徒数の急激な増加もそうですが、両親の働き方も、両親ともフルタイム勤務の方が本当に増えたなと感じるのと、よくよく聞いてみると、リモート勤務中心で仕事をされている方も多く、子育てだけでなく、両親の仕事をするスタイルも千差万別で、いろいろな形態があることに驚きます。
文部科学省の調査によると、不登校児童生徒数は、コロナ禍前の2019年中学生127,922人、小学生53,350人の合計181,272人だったのが、コロナ禍後となる5年後の2024年には、中学生216,266人(169%増)、小学生137,704人(258%増)の合計353,970人(195%増)となっています。小学生の不登校が急増しているのは、2019年末から始まったコロナ禍の影響が大きいものと思われますが、子どもを教える現場にいると、この状況が、元通りに収束するとは到底思えません。学校が、大きく変わらなければ、この傾向は今後も進んでいくのではと思います。
また、AIが普及し、それに関連するテクノロジーの目覚ましい進歩が起こっている中で、将来、これまで当たり前にあった仕事が無くなり、多くの人が失業して貧困に喘ぐのではという悲観的な将来ビジョンが、メディアでは毎日のように語られています。教育の現場でも、どのように子どもを教育していけば良いのか、誰も自信を持って明確な解を見出せずにいます。
現在、私は、日々子どもと接して、読むこと書くこと、考えること、挑戦すること、作ること、伝えること、表現することは、どんなに社会が変わっても、その子の実になると信じて、対話と体験をベースにしたワークショップを企画運営し、子どもに教える仕事をしているのですが、「成績が上がる」「受験に合格する」という明確なゴールを設定している塾の方が、依然として人気があり、ドリル主体のパターン学習やテスト対策中心の詰め込み教育による中学受験は、エスカレートする一方です。
教育という現場に身を置いていると、この子達の将来は、一体どうなっちゃうのだろうと、かなり悲観的で不安な気持ちになりがちです。ただ、これは、ちょっと不健全な感覚なのではないか?と思い始め、最近ちょっと視点を変えて、今現在の人同士の繋がり方や仕事のトレンドみたいなものをあれこれググって調べてみたり、個人ベースで創作・発信・販売するマイクロビジネスが集まって、大きな集客を果たしているイベントなどを覗いてみたり、話を聞いたりしています。
コミケやデザインフェスタ、クリエーターEXPOなどは、そうした同人サークルや個人を基盤にしたマイクロビジネスのイベントとしてかなり歴史があり、毎年盛り上がっているイベントです。こうしたイベントで、それなりに収益を上げる個人や団体が多く存在することは、以前より知っていましたが、私達の世代では、そうしたイベントで注目されることで、メジャーな企業に見つけてもらって仕事を貰うようになり、安定した仕事の道が拓けていく、プロになるための登竜門というイメージも強くありました。
けれど、今は、インターネットの発達により、企業の手を一切借りずに、小ロット生産で、完全に個人で質の高いものを創作し、小規模に発信して販売していくことができるようになっています。手作りのボードゲーム、カードゲームなどのアナログゲームをお互いに披露し、試遊して、その場で販売するゲームマーケットは、2010年までは年1回、2011年春から年2回台東区の台頭館で開催していたものが、2013年春からコミケ同様、東京ビッグサイトでの年2回の開催となり、昨年2024年秋からは、幕張メッセで開催と、コロナ禍を挟んで順調に成長して規模を大きくしています。2025年春には、幕張メッセ4ホールで、一般出展の2日間延べ参加数1,440、企業出展両日とも80社で、2日間合計の参加者総数のべ27,000人を集客しています。年2回開催されており、京都や大阪、神戸などの関西でも定期開催され、いずれも盛況を極めています。
また、インディー系デジタルゲームの国内最大規模のイベントであるビットサミットも2013年約40組の出展者で来場者数170人で京都のみやこめっせで始まったものが、毎年恒例開催され、 年々大規模化しコロナ前の2019年には17,038人を集客しました。その後コロナ禍での自粛期間のオンラインイベント開催を経て、2022年よりみやこめっせでの開催を再開し、今年の2025年夏には、ビジネスデー1日、一般公開2日間、計3日間開催し、300超のブースが出展、会場からのオンライン配信や限定グッズ配布など各ブース毎にファンコミュニティー向けのプロモーションに力を入れるなど、会場だけにとどまらない大規模な集客・動員を実現しています。インディーゲームの、ビットサミット会場での試遊→コンテスト開催→クラウドファンディングの実施→スポンサー企業とのマッチング→新作ゲーム制作というビジネス化への大きな流れもできつつあり、フラットに企業やクリエイター個人、ファンである一般人が交流し、同好の士の大規模コミュニティーが経済的な力を持って構築されてきています。
2002年11月に大塚英志氏の呼び掛けで始まった文学フリマは、第一回目にして約80の団体・個人からの出店が集まり、当初は文人主導の文学イベントの試みでした。その後有志による文学フリマ事務局が結成され、ボランティアによる運営を開始し、プロ・アマ入り乱れての文学系同人誌即売会として徐々に規模を拡大していきました。有志による地方での文学フリマ開催も、徐々に全国に広がっていき、2008年以降、文学フリマ東京は、年2回定期開催に移行しています。2009年12月の文学フリマ東京の出店数は約380、参加者は出展者、一般来場者合わせて約2,400人でしたが、コロナ直前の2019年5月には、TRC第一展示場で開催し参加者数は、5,166人となり、初めて5,000人を超えました。この頃には、京都、広島、前橋、金沢、大阪、岩手、札幌、福岡など全国主要都市でも、文学フリマが開催され、それぞれ来場者も過去最多を記録して盛況となって来ています。コロナ禍でのイベント中止期間を経て再開後、2023年5月TRC第一展示場開催の文学フリマ東京37では、1,601ブース、1,435出店となり、来場者数が1万人を突破し、出展者を除く一般来場者数も8,453人に昇っています。翌2024年12月には、会場を有明ビッグサイトに会場を移し、2,263出店、2,578ブースを集め、来場者数は、14,967人(出展者4,026人、一般来場者10,941人)と、一般来場者のみで1万人を超える集客規模の一大イベントに成長しています。今年度2025年11月の文学フリマ東京41も、有明ビッグサイトにて開催され、参加者のnote.記事執筆やSNS発信などが盛んに掲載され、いよいよ大きな影響力を持つ大規模集客イベントとして育って来ていることが実感されました。
文学フリマ↓
https://bunfree.net
これらのフェス型イベントが、幕張メッセや有明ビッグサイトの定番のビジネス見本市と全く異なるのは、個人や同人、インディーズの作品披露即売会という、基本的に個人やサークル、スタートアップ・ユニットの同好の士の集まりだということです。もちろんプロのクリエイターやプランナー、プロデューサー、プログラマーといった人達も、優秀な仲間やビジネスのシーズを探しにやって来ますが、エンスーやコレクター、マニアといった人達も、作り手として出展しており、ファンやマニアという一般人や、これからオリジナルのものを作ろうと思っている人達も集まります。作り手が、自分たちが作ったものを説明し、披露し、同好の士と一緒に盛り上がって、お互いに繋がってビジネスしたり助け合ったり、コラボしたりする一大同人コミュニティが、幕張メッセや有明ビッグサイト規模で、大企業や代理店の想像を超えた集客を実現し、今後も成長していくトレンドにあるということです。
企業主導の場合でも、インターネット文化から生まれたIT企業の場合、上記のような同人コミュニティの形成に成功しているケースもあります。ハンドメイドクラフト・手芸の世界で、赤丸ホールディングス株式会社(現:株式会社クリーマ)が、2010年5月にハンドメイド作家と顧客を直接結びつけるオンラインのマーケットプレイスとして、Creemaを立ち上げ、その後多数の競合他社参入の中、2013年7月にクリエイターの祭典「ハンドメイドインジャパンフェス(HMJ)」の東京ビッグサイトでの初開催に踏み切っています。この大規模イベント以降、地方でのさまざまなクラフトイベントとのコラボイベントを積極的に開催し、2015年には、Creemaへの出品作品数が100万点を超え、日本最大のハンドメイドクラフトのオンラインマーケットプレイスに成長し、2020年には東証マザーズに上場を果たしています。2023年には、ハンドメイドジャパンフェスも10周年を迎え、2026年1月にも、有明ビッグサイトで2日間の開催が予定されています。こうしたインターネット通販の個人作家やインディーズ・ユニットと、顧客をダイレクトに繋げるマーケットプレイスプラットフォームが主導して、有明を初めとする全国各地のリアルイベント開催、個人やインディーズ・ユニットの作家活動を支えるクラウドファンディングなどのサービスも展開し、現在登録作品数1,400万点、作家数24万人、月間13億円以上の流通額を生み出すビッグビジネスに成長しているのです。
学校に行かなくなってしまった子ども達の将来は、どうなっていくのだろう?という心配は、こうした社会の大きな変化をつぶさに調べたり観て回ったりする中で、今私の中では徐々に小さくなって来ています。現在の学校の個性も趣味も価値観もバラバラの大きな集団に適応しなければ生きていけない時代は、終わりつつあるのではないかと考えるようになって来ました。趣味が合い、気の合う仲間数人と同人サークルを立ち上げることができれば、そこから自分達が居心地良く楽しく生きていく居場所に辿り着くことができるのではないかという温かく優しい未来が見えて来るような気がしています。我々大人達は、一人一人の子どもの好きなこと、興味・関心があるものを起点にして、その子が繋がれる同人コミュニティに接続する機会を作ってあげること、一緒にその世界でのさまざまな人や物事との出会いを楽しんでいけば良いのかもしれません。ゲームマーケットでも、ベビーカーを押して観て回る家族連れを、ちらほら見かけました。ポケモンのブースでは、親子で楽しめるカードゲーム試遊コーナーを一際大きなスペースで展開しており、親子連れが少なめでマニアが中心になると聞いていた土曜日でも、活況を呈していました。親子連れが増える日曜日は、大賑わいになるでしょう。
これまでの常識に捉われず、親子で一緒に楽しめそうな同人コミュニティ・イベントを探して行き、子どもが共感・共鳴する人達と繋がれる場を探す旅を子どもと一緒に、自分も楽しみながら進めていけば、普通に学校に毎日通えなくても別に困らないのではと、小さな希望の確かな光がさすような心持ちになりました。そこから先は、子ども自身の冒険ですから、温かく見守っていけば、それで良いのかもしれません。
・・・・・・・・・・・・・・・・
◆PonoLipo Club Workshop & Library
3,500冊余りの英語と日本語の図書を揃えたライブラリーサービス付きのワークショップです。曜日毎にSTEAM系、英語多読&Phonics、読書&作文の書くワークショップが、ほぼマンツーマンの指導で開講されています。対象年齢は、4〜12歳。物語絵本・児童書から図鑑、事典、科学図書、学習図書まで、幅広い分野の厳選された教育的で夢中になれる図書が揃っています。
PonoLipo Clubのご案内HPは、こちらから↓
PonoLipo Clubへのお問い合わせは、メールにて下記までお願いいたします↓
▶︎ miodaka@ponolipo.com
〒152-0035
住所:東京都目黒区自由が丘2-18-15 1F
TEL&FAX:03-5726-9936
E-mail miodaka@ponolipo.com